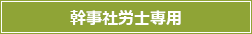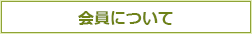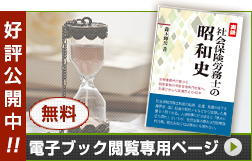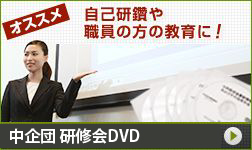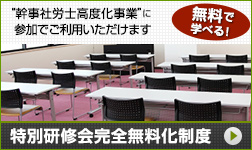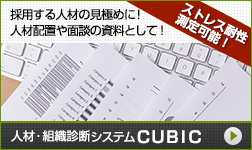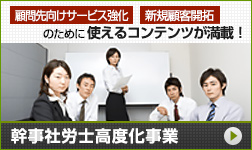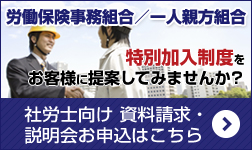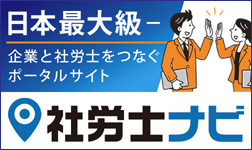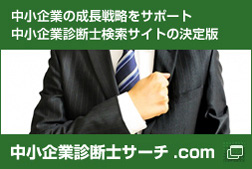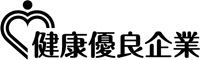トップページ ≫ サービス一覧 ≫ NETWORK INFORMATION CHUKIDAN ≫ 業種特化社労士の視点から
NETWORK INFORMATION CHUKIDAN
業種特化社労士の視点から(第54回 『介護業界編』)
<坂上 雅幸 氏>
●介護業界との出会いと原点
私は大阪府の自治体で約5年間、介護保険法に基づく指導監査業務を担当していました。事業所にとって「監査」は緊張を伴う場であると同時に、制度や運営に関する日ごろの疑問や不安を相談できる、数少ない機会でもあります。実際、労務管理だけでなく、加算要件や記録整備、運営体制の不備など、制度運用の細部に課題を抱える事業所は少なくありませんでした。私はその現場で、「もっと身近に相談できる支援者が必要ではないか」と強く感じるようになりました。
この想いこそが、私が介護業界を専門に支援するようになった原点です。
とくに印象に残っているのは、ある小規模事業所での出来事です。そこでは就業規則が整備されておらず、労働時間の管理も曖昧なまま長年運営されていました。監査の際に制度の重要性とリスクについて丁寧に説明したところ、後日あらためて相談があり、労務体制の見直しや加算申請のサポートへとつながりました。現場の声に耳を傾け、制度を現実の中に落とし込んでいく支援の大切さを実感した経験です。
●介護業界における課題と社労士としての支援
介護事業所の経営者や管理者は、現場に立ちつつ、事務作業や職員管理にも追われる多忙な日常を送っています。中小規模の事業所では特に、労務管理や制度対応が後手に回りがちです。
介護業界の労働環境には、他業界には見られない複雑な構造があります。まず、事業の種類(日中・夜間サービス、訪問サービス、施設系サービスなど)によって、労働時間や休憩、休日の設計が大きく異なります。変形労働時間制の導入可否や、夜勤・宿直に関する手当の設計など、サービス内容と職員の働き方を把握した上で、制度設計を行う必要があります。
また、処遇改善加算やキャリアパス要件の整備においては、資格、雇用形態、職種ごとの整理が不可欠です。正社員、パート、派遣社員では賃金体系や評価制度が異なるため、それぞれに適した制度設計が求められます。介護業界特有の多職種構成と多様な雇用形態を理解し、制度の目的と現場の実情を照らし合わせながら制度を運用する視点が、現場から信頼される支援には不可欠です。
近年は、BCP(事業継続計画)の策定支援も重要性を増しています。自然災害や感染症など、突発的な事象により介護サービスの継続が困難となるリスクに備え、体制を整える必要があります。厚生労働省が策定を義務づける方針を打ち出して以降、当事務所へのBCP支援依頼も増加しています。緊急時の職員配置、優先業務の明確化、連絡体制の整備、外部関係機関との連携といった観点から、実態に即した計画作成を支援しています。ある事業所では、地域の防災訓練に合わせて独自の避難マニュアルを作成し、実地訓練を組み合わせることで、職員の意識向上と実効性の高いBCP策定につながった事例もあります。
●介護業界ならではの支援の難しさと信頼関係
介護業界にあまり詳しくない社労士が顧問をしていることで、制度への対応や加算の申請に不安を感じ、「社労士を変更したい」と相談されることがあります。制度を理解するだけでなく、介護業界特有の雰囲気や文化、行政とのやり取りの特徴まで考慮する必要があり、そこがこの業界を支援するうえでの難しさであり、同時にやりがいでもあると感じています。
介護事業は、自治体からの許可を受けて行う事業であり、定期的な指導や監査、報酬の見直しなど、行政との関係がとても深い業界です。社労士としては、通常の労働基準監督署や年金事務所への対応に加えて、各自治体のルールや対応の仕方もよく理解しておく必要があります。幅広い知識と状況に応じて柔軟に動ける力が求められます。
また、介護業界では、労務だけでなく事業運営そのものに関わるような支援を求められることも多くあります。たとえば、管理者の交代にともなう届け出や、介護報酬加算の取得支援など、行政への手続きと労務の両面をカバーする支援が必要になります。こうした支援はケースごとに内容が異なり、社労士としての専門性も広がります。
さらに、介護の現場を支えるには、制度の知識だけでなく、現場で働く職員の気持ちや人間関係、職場の雰囲気まで理解しながら支援することが大切です。「この制度は本当にこの事業所に合っているか?」「職員に混乱がない形でどう導入すればいいか?」といった視点を持つことが求められます。書類だけ整えるのではなく、現場に寄り添いながら進める支援こそが、本当の意味で信頼されるサポートにつながるのだと感じています。
●他士業・専門企業とのアライアンスによる支援強化
こうした多様な支援ニーズに応えるため、私は他士業や専門企業との連携にも注力しています。たとえば、介護事業に明るく、労働紛争の相談にも対応できる弁護士、会計に強い税理士、介護ソフト会社と連携した業務効率化の提案、研修会社と連携した職員育成支援、企業年金の導入による定着支援など、多様なパートナーとのアライアンス体制を構築しています。
介護事業所の現場では、労務に限らず「とにかく何でも相談したい」という空気があります。中には、「社員旅行を計画しているが法的に問題ないか?」「利用者と一緒に行事で旅行に行きたいがどうすればよいか?」といった、社労士業務の枠を超えるような相談もあります。「こんなことまで聞かれるのか」と思う場面もありますが、介護事業所から、それだけ信頼してもらえている証でもあります。もちろん、すべてに対応できるわけではなく、法的な限界や業務範囲の壁に直面して、もどかしさを感じることもあります。それでも、できるだけ多くの引き出しを持ち、必要に応じて他の専門家につなげられる体制を整えておくことで、安心して相談してもらえる関係性を築いていけるよう努めています。
●組織としての成長と顧問先の信頼
独立当初は一人で対応していましたが、現在では、介護業界に関する知識や経験をスタッフに共有・育成することで、組織としてより多くの課題に対応できるようになりました。スタッフが育つことで、私自身が対応できる業務の幅も広がり、顧問先のニーズに対してより迅速かつ柔軟に応えることができる体制が整いつつあります。
また、ありがたいことに、顧問先からスタッフに対して「丁寧に話を聞いてくれて安心した」「制度の説明がとても分かりやすかった」「質問にすぐ対応してくれて助かった」といったお声をいただくことが増えています。スタッフへの信頼の高まりは、事務所全体への評価にもつながっており、「この事務所にお願いしてよかった」「スタッフの方にも感謝しています」と直接お礼の言葉をいただく機会も少なくありません。こうした声をいただけることが、何よりの励みであり、スタッフとともに成長していく喜びを日々実感しています。
スタッフは通常の社労士業務に加えて、介護事業の知識と経験を積むのに時間がかかりますが、成長すれば非常に頼もしい戦力になります。そのため、所内スタッフが働きやすく、学び続けられる環境づくりにも力を入れています。業務の可視化、定期的な学習機会の提供、意見を出しやすい風土づくりなど、さまざまな工夫を重ねています。特に福利厚生の充実に注力し、安心して長く働ける職場環境の整備を進めています。
実際に、制度用語すら知らなかったスタッフが、数ヶ月の実務経験と研修を経て加算制度や労働時間制度を理解し、半年後には顧問先への制度説明や簡単な運用支援を一人でこなせるようになった例もあります。こうした成長を目の当たりにすることで、育成の手ごたえと組織としての厚みが増していくのを感じています。
●むすび
介護業界は、今後も人材不足や制度改正の影響を大きく受ける分野です。だからこそ、社労士には労務や制度の枠を超えて、現場に寄り添った支援が求められています。私たちは、変化に柔軟に対応しながら、実務に根ざした伴走型の支援を重ね、介護事業者の安定と成長に貢献していきたいと考えています。制度・現場・人材を一体的に支援し、ともに成長していく姿勢をこれからも大切にしていきます。